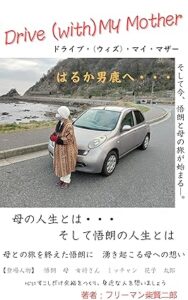フリーマン柴賢二郎の流儀
~そよ風に吹かれて、ゆっくりと歩いていこう~
世の中に起きている不思議なことや、
ふと浮かんだ疑問などをゆる~く書き綴る
何の専門家でもない私が経済的・時間的・人間関係の自由を得て、
人生のこと、世の中のこと、幸せについてなど、
一般庶民の目線で考える
「北朝鮮拉致問題とメディア報道の変遷 ― 風化との闘い」
北朝鮮による日本人拉致問題が大きく報じられるようになったのは、2002年の小泉純一郎首相の訪朝がきっかけである。
金正日総書記が公式に拉致を認め、謝罪したことで、この問題は一気に国民の関心事となった。
しかし、あれから20年以上が経ち、メディア報道のあり方は大きく変化してきた。
本稿では、拉致問題とメディアの関係を「報道の盛り上がり」「関心の低下」「風化の危機」という3つの時期に分けて書いていく。
前稿の続編という形でお読みいただけたらと思う。。
第1期:報道の衝撃 ― 「国家犯罪」の発覚
1970〜80年代、日本各地で若者や主婦が突然行方不明になる事件が相次いだ。
当時は「失踪」や「駆け落ち」と扱われ、北朝鮮の関与を報じるメディアはなかった。
転機となったのは1987年の大韓航空機爆破事件である。
北朝鮮の工作員・金賢姫が「日本人女性から日本語を習った」と供述し、拉致疑惑が現実味を帯びた。
しかし当時、日本の大手メディアはこの証言を慎重に扱い、「根拠が不十分」「誤報の危険がある」として大きく報じなかった。
2002年、小泉首相の訪朝によって金正日が拉致の事実を認めた瞬間、メディアの論調は一変した。
「国家によるテロ行為」「前代未聞の人権侵害」として、新聞・テレビは連日大きく報道。帰国した5人の被害者と家族の再会シーンは、全国民の涙を誘った。
この時期、拉致問題は“国民的関心”となり、政治の中心議題にまで押し上げられた。
第2期:報道の停滞 ― 関心の低下と政治利用
ところが、2000年代後半に入ると、拉致問題報道の勢いは徐々に落ち着いていく。
背景にはいくつかの理由がある。
まず、北朝鮮との交渉が進展しなかったこと。
5人の帰国以降、他の被害者については情報がほとんど得られず、メディアも「新しいニュース」が出しにくくなった。
次に、政治的な思惑である。
拉致問題は、国内政治の中で「保守の象徴」として扱われることが増え、政治家による“利用”が批判される場面もあった。
報道もそれに合わせて立場が分かれ、論調が統一されなくなった。
また、同時期に他の大事件や国際問題が次々と発生したことも影響した。
9.11テロ、イラク戦争、リーマンショック、東日本大震災など、メディアの関心は多方面に分散した。
結果として、拉致問題は“古いニュース”として扱われがちになっていったのである。
第3期:風化との闘い ― 「忘れさせない」ための報道
2010年代に入ると、拉致被害者の家族の高齢化が進み、訴えの声が切実さを増していった。
横田めぐみさんの母・早紀江さんをはじめ、家族会のメンバーが全国で講演や署名活動を行い、「風化させない」という強いメッセージを発信し続けた。
この時期、メディアの役割は「スクープ」ではなく、「記憶の継承」に変わったといえる。
NHKの特集番組やドキュメンタリー、民放による定期的な特集放送など、拉致問題を後世に伝える報道が増えた。
一方で、SNSの時代となり、情報の受け取り方が個人化した。
ニュースアプリやSNSでは、興味のある人だけが情報に触れる構造となり、結果として社会全体の関心は薄れている。
報道の現場でも「視聴率が取れない」「数字にならない」という理由で放送時間が削られることがあるという。
だが、ジャーナリズムの本来の使命は「注目されること」ではなく、「知らせること」である。
風化を防ぐには、メディアがこの使命を改めて自覚する必要があるような気がする。
メディアと国民意識の関係
メディア報道が減れば、国民の関心も薄れる。
関心が薄れれば、政治が動かなくなる。
つまり、報道・世論・政治は互いに連動しているのだ。
拉致問題が政治の議題として扱われ続けるためには、国民が関心を持ち続けることが不可欠であり、その“火種”を保つのがメディアの役割である。
また、私たち視聴者にも責任がある。
報道を「自分とは関係ない話」として流してしまえば、問題は静かに忘れ去られていってしまう。
ニュースを見たときに「どうして今も解決していないのだろう」と一度立ち止まる――その小さな意識の積み重ねが、世論を形づくるのだ。
一般庶民の願い
私たち一般の国民の願いは、ただ一つである。
「被害者が一日も早く帰国できるよう、社会全体で声を上げ続けたい」ということだ。
報道は、単なる情報ではない。
誰かの人生を伝え、共感を生み、行動を促す力を持っている。
だからこそ、メディアがこの問題を忘れずに伝え続けることが、被害者と家族にとっての希望になるのだ。
北朝鮮による拉致問題は、ニュースとしての「出来事」ではなく、今も続いている現実である。
そしてその現実を照らす光が消えぬようにするのは、メディアだけでなく、私たち国民一人ひとりの関心が重要なのである。
※フリーマン柴賢二郎の著書をアマゾンで販売中です。
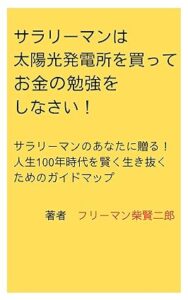
ドライブ・(ウィズ)・マイ・マザー | フリーマン柴賢二郎 | 小説・サブカルチャー | Kindleストア | Amazon