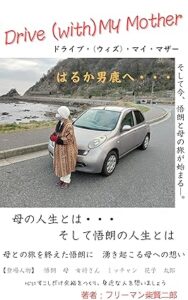フリーマン柴賢二郎の流儀
~そよ風に吹かれて、ゆっくりと歩いていこう~
世の中に起きている不思議なことや、
ふと浮かんだ疑問などをゆる~く書き綴る
何の専門家でもない私が経済的・時間的・人間関係の自由を得て、
人生のこと、世の中のこと、幸せについてなど、
一般庶民の目線で考える
日銀の役割とは?
お金のテーマが続いているが、今回は「日銀」について勉強していきたい。
――国の「お金の心臓」としての働き――
1.日銀はどんな立場の機関?
日本銀行、通称「日銀(にちぎん)」は、日本の中央銀行。
ふつうの銀行(みずほ銀行やゆうちょ銀行など)は企業や個人を相手にお金を預かったり貸したりするが、日銀は「銀行のための銀行」であり、国全体の金融システムを支える特別な存在。
たとえるなら、日銀は「国のお金の心臓」。お金という“血液”を、日本経済という“体”のすみずみに流す役目を担っている。
2.主な3つの仕事
日銀の仕事は大きく分けて3つある。
(1)お金(紙幣)を発行する
1万円札や千円札などを発行できるのは、日銀だけだ。紙幣には「日本銀行券」と印字されており、日銀こそが日本円の唯一の発行者である。
(2)物価を安定させる
モノの値段(物価)が急に上がったり下がったりすると、家計や企業の計画が立てにくくなる。
日銀は金利の調整などを通じて、「物価が安定してゆるやかに上がる状態(インフレ率2%目標)」を目指している。これを金融政策という。
(3)金融システムを安定させる
銀行が倒産したり、金融市場が混乱したりしないように、日銀は「銀行の銀行」として資金を貸し出すことがある。まるで“最後の砦(とりで)”のような存在だ。
3.政治との関係
日銀は、政府から独立した立場を持っている。
たとえば総理大臣でも「お金をもっと刷れ」と命令することはできない。政治の都合でお金を増やしすぎると、物価が暴走して国民生活が混乱するおそれがあるからだ。
ただし完全に別ではなく、政府と日銀は「車の両輪」のような関係。
政府が経済政策を立て、日銀が金融政策で支える。お互いが連携しながら、日本経済の安定を目指しているのである。
4.銀行との関係
日銀はふつうの人の口座を持たない。
その代わりに、民間銀行が日銀に口座を持っている。
たとえば「三菱UFJ銀行」が「お金を移動したい」ときには、日銀のシステムを通してやり取りする。
また、日銀が市場にお金を供給すると、銀行は企業や個人にお金を貸しやすくなり、景気が活発になることがある。こうした仕組みを通して、日銀は間接的に私たちの暮らしにも影響を与えているのだ。
5.諸外国の中央銀行との違い
世界の多くの国にも中央銀行というものがある。
アメリカではFRB(連邦準備制度理事会)、ヨーロッパではECB(欧州中央銀行)、イギリスではイングランド銀行が有名だ。
それぞれの国で役割は似ているが、日銀にはいくつかの特徴がある。
(1)独立性が比較的強い
日銀は法律上、政府からの直接的な指示を受けにくく設計されている。これは政治の影響で物価が不安定になるのを防ぐためだ。
一方、アメリカのFRBも独立しているが、議会への説明責任が非常に重く、「独立と監視のバランス」がとられている。
(2)長期のデフレ対策が課題
日本は1990年代から物価がほとんど上がらない「デフレ」に悩まされてきた。
そのため、日銀は世界の中央銀行の中でも特に長く、金利をゼロやマイナスにするなど超緩和政策を続けてきた点が特徴的だ。
(3)少子高齢化と円の信頼性
欧米と違い、日本では人口減少が進む中での金融政策が課題となっている。
ただし、「円」は世界的に信頼の厚い通貨であり、危機の時には「安全資産」として買われることも多い。
6.庶民の目線から見た「日銀への期待」
私たち一般の生活者にとって、日銀の働きは目に見えにくい。
けれども、物価が安定し、金利が適度に保たれ、給料や物価のバランスがとれている背景には、日銀の地道な努力があってこそなのだ。
もし日銀がうまく機能しなければ、
・物価が急に上がって生活が苦しくなる
・円の価値が下がって輸入品が高くなる
・銀行が不安定になりお金が引き出せなくなる
といったことが起こるかもしれない。
だから庶民の目線で言えば、日銀には、
「安心してお金を使える世の中を守ってほしい」
という期待が込められているのだ。
まとめ
日銀は「お金を発行する」「物価を安定させる」「金融システムを守る」という3つの大きな使命を持つ、国の金融の中枢である。
政府や銀行、そして世界の中央銀行と連携しながらも、最終的には国民の安心した暮らしを支えることが、その存在意義なのだ。
※フリーマン柴賢二郎の著書をアマゾンで販売中です。
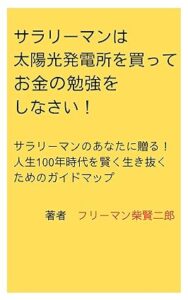
ドライブ・(ウィズ)・マイ・マザー | フリーマン柴賢二郎 | 小説・サブカルチャー | Kindleストア | Amazon