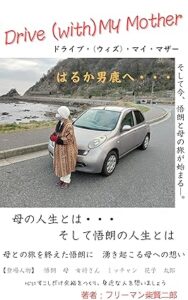フリーマン柴賢二郎の流儀
~そよ風に吹かれて、ゆっくりと歩いていこう~
世の中に起きている不思議なことや、
ふと浮かんだ疑問などをゆる~く書き綴る
何の専門家でもない私が経済的・時間的・人間関係の自由を得て、
人生のこと、世の中のこと、幸せについてなど、
一般庶民の目線で考える
日本の高齢者が持つ資産と、その行方
家計金融資産2200兆円における高齢者の保有割合
日本の家庭が持っているお金や株、預金などをあわせた「家計の金融資産」は、2025年の現在、全部でおよそ2200兆円といわれている。
これは世界でもトップクラスの金額となる。
そのうちの6割以上、つまり1200兆円以上を60歳以上の高齢者が持っているとされている。
特に70代以上の人たちが大きな割合を占めていて、日本の資産は高齢者に集中しているのが現状。
身寄りのない高齢者の資産の行方
では、その高齢者が亡くなったとき、家族や親戚がいなかったら、その財産はどうなるのだろうか。
日本の法律では、相続人がいない場合、その人の資産は最終的に国(国庫)のものとなる。
ただし、すぐに国に渡るわけではなく、家庭裁判所が「清算人」を選び、借金や未払いの税金などを整理したあとに残った財産が国に帰属する。
実際に、こうした「相続人がいない遺産」は近年増えていて、国に入る額も毎年1000億円を超えるほどになっている。
国庫に帰属された資産の使途
では、国に入ったお金はどう使われるのか?
実は法律で「必ずこの分野に使う」と決められているわけではなく、最終的には国の一般的な収入の一部となるそうだ。
そのため、国の借金返済や社会保障、教育、道路や橋といったインフラ整備など、さまざまな用途にあてられる可能性がある。
一方で、「せっかくの財産なのだから、高齢化対策や福祉に重点的に使うべきだ」という意見もある。
国に帰属する遺産が今後さらに増えると予想されるだけに、その使い道をどうするのかは社会全体で考えていくべきテーマといえるだろう。
まとめ
日本の2200兆円にものぼる金融資産は、高齢者に大きく偏っている。
家族のいない高齢者が亡くなった場合、その資産は国のものとなる。
そして国は、そのお金を社会全体のために使うことになる。
ただし、その具体的な使い方はまだ十分に議論されてはいないのが現状。
高齢化社会が進む中で、「誰のために、どんなふうに使うのか」を決めていくことが、これからの日本にとって大切な課題となっている。
※フリーマン柴賢二郎の著書をアマゾンで販売中です。
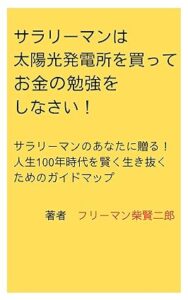
ドライブ・(ウィズ)・マイ・マザー | フリーマン柴賢二郎 | 小説・サブカルチャー | Kindleストア | Amazon