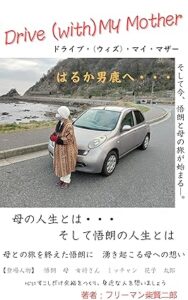フリーマン柴賢二郎の流儀
~そよ風に吹かれて、ゆっくりと歩いていこう~
世の中に起きている不思議なことや、
ふと浮かんだ疑問などをゆる~く書き綴る
何の専門家でもない私が経済的・時間的・人間関係の自由を得て、
人生のこと、世の中のこと、幸せについてなど、
一般庶民の目線で考える
日本の「デジタル赤字」とは何か――原因・背景・そして私たちの願い
デジタル赤字とは何か
近頃、「デジタル赤字」という言葉を耳にすることが増えた。
これは、海外との取引において、デジタル関連の支出が収入を上回っている状態を指す。たとえば、日本企業や個人が海外のクラウドサービス、アプリ、広告プラットフォームなどを利用し、その利用料を海外に支払っている。
こうした支払いが、逆に日本企業が海外から得る収入より多いと、結果として「赤字」になるのだ。
つまり、モノの貿易でいえば「輸入超過」と同じである。
ただし、ここで扱うのは「デジタルサービス」という目に見えない取引である点が特徴だ。
実際、日本は2020年代に入ってからデジタル赤字が急拡大し、2024年には過去最大の6.7兆円規模に達したとされている。
デジタル赤字が生まれる理由
デジタル赤字の最大の原因は、日本がデジタル技術を「使う側」になっていることにある。
たとえば、私たちが毎日使っているGoogle、YouTube、Amazon、Netflix、X(旧Twitter)など、主要なデジタルサービスの多くはアメリカの企業が提供している。
日本の企業が広告を出したり、クラウドを利用したりすれば、その利用料は当然アメリカ本社へと流れていく。
さらに、近年では企業活動の中心がデジタルに移っている。
データの保存、AIの分析、リモートワークの仕組みなど、あらゆる面でクラウドが欠かせない。
そのクラウド市場を支配しているのがAmazon(AWS)、Microsoft(Azure)、Google(GCP)といった米国勢だ。
結果として、日本の企業はこれらのサービスを大量に利用し、毎年多額の費用を海外に支払っている。
また、日本のソフトウェア産業の構造にも問題がある。
かつて日本は家電や半導体など「ハードウェアの国」として世界をリードしていた。
しかし、インターネット時代に入り、価値の中心がハードからソフトへと移ったとき、日本企業は十分に対応できなかった。
ソフトウェア開発力やデジタルビジネスの発想が弱く、国内発のプラットフォームが育たなかったのである。
加えて、教育や人材の面でも課題は大きい。
日本では依然として「文系」「理系」が分かれた教育が続いており、デジタルを総合的に理解して活用できる人材が少ない。
AIやデータ分析を扱えるエンジニアの数も、アメリカや中国に比べて圧倒的に不足している。
今後の見通し
では、このデジタル赤字は今後どうなるのか。
残念ながら、短期的には赤字がさらに拡大する可能性が高い。
AI、クラウド、デジタル広告など、どれも成長分野であり、需要は今後も増えるからだ。日本企業や自治体がDX(デジタルトランスフォーメーション)を進めるほど、海外企業への支払いが増えるという矛盾が生まれている。
一方で、希望がないわけではない。
日本国内でも、AI技術やクラウド代替サービス、デジタル人材の育成に力を入れる動きが出てきている。
政府も「デジタル庁」や「スタートアップ育成5か年計画」などを通じて、国産のデジタル基盤を育てようとしている。
これが実を結べば、将来的には海外依存の割合を減らすことができるかもしれない。
ただし、そのためには時間がかかる。
海外勢が築いた巨大なエコシステムは、一朝一夕では覆せない。
日本企業が世界で通用するソフトウェアやプラットフォームを開発するには、長期的な投資と、失敗を許容する文化が必要だ。
一般庶民の願い
デジタル赤字という言葉を聞くと、「国や企業の問題であって、自分には関係ない」と思う人もいるかもしれない。
だが、実際には私たちの生活とも深くつながっている。
赤字が拡大すれば、国全体の所得が海外に流出し、国内の経済が細る。
企業の利益が減れば、給料や雇用にも影響が出るかもしれない。
それに、もし海外企業のサービスに過度に依存していると、価格改定や規約変更などに日本全体が振り回されることにもなりかねない。
私たちが毎日使っているSNSや検索エンジンがすべて海外製というのは、ある意味で「デジタル主権」を失っている状態でもある。
だからこそ、私たち庶民の願いはシンプルだ。
「日本発のデジタル技術で便利な暮らしを支えたい」
ということだ。
海外の真似ではなく、日本の強み――細やかさ、信頼性、安全性――などを活かしたサービスを育ててほしい。
たとえば、高齢者にも使いやすいアプリ、地域の中小企業が気軽に利用できるクラウド、日本語文化に根ざしたAIなど、まだまだ可能性はある。
また、個人としてもデジタルリテラシーを高める努力が必要だ。
AIやデータを使いこなす力を身につければ、単なる「利用者」ではなく「創り手」になることができる。
そうした人が増えれば、日本全体のデジタル力も確実に底上げされるだろう。
おわりに
デジタル赤字は、単なる経済の数字ではない。
日本が「未来をどのように生きるか」を映す鏡でもある。
今は確かに海外企業に依存しているが、それは同時に、日本がまだ伸びしろを残している証拠でもある。
私たちが技術を学び、企業が挑戦を恐れず、国が長期的視点で支援を続ける。
そんなサイクルが回り始めたとき、デジタル赤字は「デジタル黒字」へと変わる日が来るだろう。
※フリーマン柴賢二郎の著書をアマゾンで販売中です。
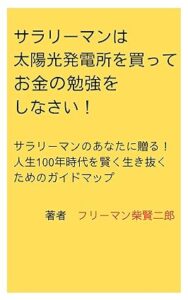
ドライブ・(ウィズ)・マイ・マザー | フリーマン柴賢二郎 | 小説・サブカルチャー | Kindleストア | Amazon