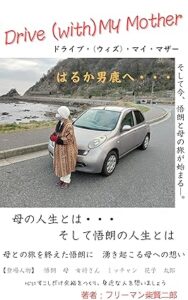フリーマン柴賢二郎の流儀
~そよ風に吹かれて、ゆっくりと歩いていこう~
世の中に起きている不思議なことや、
ふと浮かんだ疑問などをゆる~く書き綴る
何の専門家でもない私が経済的・時間的・人間関係の自由を得て、
人生のこと、世の中のこと、幸せについてなど、
一般庶民の目線で考える
投資家としての「メンタル管理」
投資における「心のコントロール」──メンタル管理の大切さ
投資という言葉を聞くと、多くの人は「お金を増やすための行動」だと考える。
もちろんそれは間違いではない。
しかし、実際に投資の世界に足を踏み入れると、ただ知識や経験だけでは上手くいかないことを思い知らされる。
そこに大きく関わってくるのが「メンタル(心)の管理」だ。
投資とは、数字と向き合うように見えて、実は「自分の感情」との戦いでもあるのだ。
1.感情が生む「判断ミス」
投資を始めたばかりの人がよく陥るのが、「焦り」と「恐れ」だ。
株価が少し上がると「もっと上がれ!」と興奮し、逆に下がると「もうダメだ」と何も手に付かないほど不安になる。
このような感情に振り回されると、冷静な判断ができなくなる。
たとえば、ある株を買ってすぐに値下がりしたとする。
そのとき、「早く損を取り戻したい」と焦って別の銘柄を衝動的に買ってしまうことがある。
しかし、それは「感情での判断」であり、「分析による判断」ではない。
結果的に損を広げてしまうケースが多いのだ。
投資の世界では、「感情は最大の敵」とよく言われる。
利益を得るために必要なのは「正しい情報」と「冷静な判断」。
そのどちらも、心が乱れていては働かないのである。
2.メンタルを崩す三つの罠
投資家を不安定にする心の罠には、大きく三つある。
① 欲の罠
「もっと儲けたい」という欲は、人間なら誰しも持っている。
しかし、それが強すぎると、無理な投資をしてしまう。
自分の許容範囲を超えて資金をつぎ込み、少しの変動で大きなダメージを受ける──これは典型的な失敗パターンだ。
② 恐怖の罠
損を出したくないという気持ちは自然なものだが、過度に恐れると何もできなくなる。
チャンスが来ても「また損をしたら嫌だ」と動けない。
すると、時間だけが過ぎていく。
投資で大切なのは「恐れをなくすこと」ではなく、「恐れと上手く付き合うこと」なのだ。
③ 群集心理の罠
「みんなが買っているから自分も買おう」と考えるのも危険だ。
人の流れに乗ることで安心感は得られるが、相場は常に「多数派が勝つ」とは限らない。むしろ、冷静に群れから一歩引いて見られる人こそが、チャンスをつかむのだ。
3.心を整えるための三つの習慣
では、どうすればメンタルを安定させて投資と向き合えるのだろうか。
ポイントは「習慣づけ」だ。
① ルールを決める
感情に流されないためには、あらかじめ「売買のルール」を作っておくことが大切だ。
たとえば、「〇%上がったら売る」「〇%下がったら損切りする」といったルールを決めておけば、迷いが減る。
ルールは冷静な自分が作り、実行するのは熱くなりやすい自分──つまり「過去の冷静な自分が未来の自分を助ける」仕組みだ。
② 記録をつける
取引内容とそのときの気持ちを日記のように記録しておくと、自分の弱点が見えてくる。「焦って買ったときは失敗が多い」「不安なときほど売り急いでいる」など、心の傾向がわかれば、それを修正できる。
投資ノートは「自分のメンタルを映す鏡」とも言える。
③ 休む勇気を持つ
相場が荒れているとき、無理に取引を続けるのは危険だ。
心が疲れたと感じたら、一度離れて休むことも大切。
スポーツ選手がコンディションを整えるように、投資家にも「休養の時間」が必要なのだ。
4.「勝つ」よりも「続ける」
多くの人は投資に「勝ち負け」のイメージを持つが、本当に大切なのは「続けること」。短期的な勝ち負けよりも、長く安定して投資を続けられる人が最終的に成果を出す。
そのために必要なのが、冷静さを保つ「心の強さ」である。
メンタル管理とは、「心を強くすること」ではなく、「心が揺れることを受け入れる力」を育てることだ。
誰だって感情は動く。
大事なのは、動揺しても立て直せる自分をつくること。
5.おわりに
投資はお金のゲームではなく、「自分との対話」だ。
数字の裏にあるのは、他人の心理、そして自分の心理。
市場がどんなに荒れても、自分の心が穏やかでいられるように。
最も大きな利益は、実は「メンタルの安定」なのかもしれない。
さて、このように投資の賢人たちからの言葉をまとめてみたが、自分はどこまで感情を捨て、冷静でいられるか、謙虚に向き合いたいと思う。
※フリーマン柴賢二郎の著書をアマゾンで販売中です。
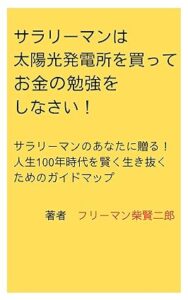
ドライブ・(ウィズ)・マイ・マザー | フリーマン柴賢二郎 | 小説・サブカルチャー | Kindleストア | Amazon