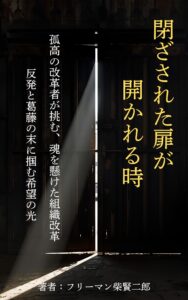フリーマン柴賢二郎の流儀
~そよ風に吹かれて、ゆっくりと歩いていこう~
世の中に起きている不思議なことや、
ふと浮かんだ疑問などをゆる~く書き綴る
何の専門家でもない私が経済的・時間的・人間関係の自由を得て、
人生のこと、世の中のこと、幸せについてなど、
一般庶民の目線で考える
宝くじの仕組みとねらい、そして人が買ってしまう理由
宝くじは、日本で最も身近な「夢のあるギャンブル」である。
当たれば一気に億万長者になれるが、現実にはほとんどの人がハズレる。
それでも多くの人が購入する。
その理由を理解するためには、宝くじの仕組み、行政側の本当のねらい、そして買う人の心理を正しく知る必要がある。
本稿では、それらを整理し、分かりやすく解説したい。
■ 宝くじの基本的な仕組み
宝くじは、都道府県と政令指定都市が発売元で、実際の販売・管理業務はみずほ銀行が受託している。
宝くじの売上はすべてが賞金になるわけではない。
むしろ、賞金は売上の約半分以下であり、残りは自治体への収益として使われる。
宝くじの売上は大まかに以下の割合で分配される。
約45%:当選金(賞金)
約40%:自治体の収益(公共事業などに使われる)
約15%:経費
この構造から分かるように、宝くじは投資商品ではなく「買った瞬間に55%負けているギャンブル」である。
つまり、長く買い続ければ続けるほど、数学的には確実に損をする仕組みだ。
■ 宝くじの“真のねらい”とは
宝くじの目的は「庶民に夢を売るため」ではない。
行政側から見れば、宝くじは税金以外で安定した財源を確保する手段である。
宝くじの収益は、以下のような用途に当てられる。
地域の福祉事業
公共施設の建設・整備
災害対策
スポーツや文化の振興
つまり、宝くじは“自主財源を作るための制度”であり、税金のように感じさせずにお金を集める仕組みとも言える。
これは「逆進性の強い税金」とも呼ばれる。
なぜなら、宝くじを多く買うのは収入の少ない人ほど多いと言われており、結果として低所得者ほど多く払っている構造になりやすいからである。
■ それでも人はなぜ宝くじを買うのか
宝くじの当選確率は非常に低い。
例えば年末ジャンボで1等が当たる確率は約2000万分の1である。
これは、ほぼ「当たらない」と言っていいレベルだ。
それでも人々が宝くじを買ってしまうのは、心理学的に次のような理由がある。
- 小さな金額で大きな夢を買える
宝くじは1枚300円。300円で“億万長者になる自分”を想像できる。これは心理的に非常に大きな魅力である。
- 確率の大小を正しく理解できない(非合理性)
人は「1/2000万」と言われても、その小ささを実感できない。脳は極端な結果を過大評価する傾向があり、億が当たる映像や広告を見るだけで「自分も当たるかもしれない」と錯覚してしまう。
- 希望を買う行為
宝くじは、人生に変化が少ないと感じている人にとって、「何かが変わるかもしれない」という希望を提供する。人は不確実でも、希望そのものに価値を感じる生き物である。
- 社会的な習慣
年末ジャンボやサマージャンボは季節のイベント化しており、買うこと自体が毎年の“風物詩”になっている。心理的ハードルが低いのも理由である。
■ 宝くじと投資の決定的な違い
宝くじと投資はよく比較されるが、本質はまったく異なる。
投資:確率的にはプラス(時間が味方する)
株式やインデックス投資は長期的に市場と企業価値が成長するため、期待値はプラスである。
宝くじ:確率的にも期待値がマイナス
構造的に半分以上が自治体に取られるため、買った瞬間から損をするゲームである。
もし「数年で人生を変える一発逆転」を期待して宝くじを買うなら、それは非常に非効率であり、むしろ計画的な積立投資のほうが実現可能性が高い。
■ まとめ
宝くじは、自治体の財源確保という明確な目的のもと運営されている仕組みであり、当選確率は極めて低い。
それでも多くの人が買ってしまうのは、人間の心理が「確率」より「夢」を重視してしまうからである。
宝くじを否定する必要はない。
300円で「もしかしたら」という夢を楽しむのも人生の一部である。
ただし、その裏側の仕組みを理解したうえで、使う金額を決めることが賢明だと言える。
※フリーマン柴賢二郎の著書をアマゾンで販売中です。
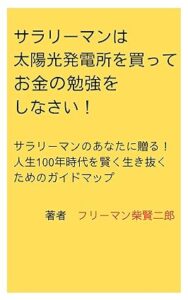
ドライブ・(ウィズ)・マイ・マザー | フリーマン柴賢二郎 | 小説・サブカルチャー | Kindleストア | Amazon
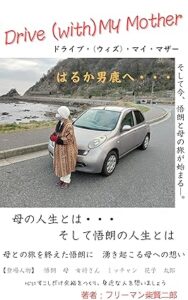
閉ざされた扉が開かれる時: 孤高の改革者が挑む魂を懸けた組織改革 反発と葛藤の末に掴む希望の光 | フリーマン柴賢二郎 | 小説・サブカルチャー | Kindleストア | Amazon