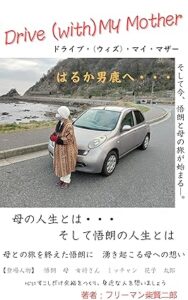フリーマン柴賢二郎の流儀
~そよ風に吹かれて、ゆっくりと歩いていこう~
世の中に起きている不思議なことや、
ふと浮かんだ疑問などをゆる~く書き綴る
何の専門家でもない私が経済的・時間的・人間関係の自由を得て、
人生のこと、世の中のこと、幸せについてなど、
一般庶民の目線で考える
太陽光パネルの大量廃棄問題について
2030年以降、太陽光パネルが大量に廃棄されるようになり、それらがどう処分されるのか、あるいはリサイクルされるのか、その費用は誰が負担するのかなど、未解決な部分が多い。
昨今、これが大きく話題になっている。
私は太陽光発電事業者であるため、パネルの廃棄問題には常に注視し動向を見守っている。
2022年ごろだったと思うが、一旦は「事業者が廃棄処分費用として11年目から積み立てる」という法律ができたと聞いたが、問題が多かったからか再び議論が過熱を帯びているようだ。
今回は太陽光パネルの廃棄問題について掘り下げ、問題の中身から始め、そもそもなぜ廃棄問題の議論が後追いになっているのか、問題の概要、現状、海外の対応、今後の見通しまでをまとめていきたい。
問題の中身
- 環境への影響
有害物質の流出リスク
太陽光パネルには鉛やカドミウムなどの有害金属が含まれている場合があり、適切に処理されないと土壌・地下水汚染につながる。
不法投棄の増加
処理コストを嫌う事業者や個人が山中や空き地に投棄する可能性が高まる。
- 廃棄物処理体制の混乱
処理施設の不足
短期間に大量の廃棄が発生すると、現行の廃棄物処理施設では対応しきれず、滞留・放置が増える。
費用負担の不透明さ
誰がリサイクル費用を負担するのか(事業者か、自治体か、消費者か)が決まっていないため、混乱が生じる。
- 経済的損失
資源循環の機会損失
パネルには銀やアルミ、ガラスなどの有用資源が含まれている。リサイクル制度がなければ資源が無駄になる。
処理コストの社会的転嫁
制度がなければ最終的に自治体や国の負担となり、税金で処理することになりかねない。
- 社会的信用の低下
再エネの信頼性への影響
「環境に優しい」とされてきた再生可能エネルギーが、大量の産業廃棄物を残すものだと社会から批判され、普及にブレーキがかかる。
国際評価の低下
EUなどではすでにリサイクル制度が整備されており、日本の制度遅れは「環境後進国」とみなされるリスクになる。
まとめると・・・
「環境汚染」・「廃棄処理の混乱」・「資源の浪費」・「社会的信頼の失墜」 が主な問題となっている。
廃棄問題が未整備のままスタートしたFIT制度
- なぜ「導入優先」になったのか
背景事情
2011年の東日本大震災と原発事故をきっかけに、再エネ拡大は「急務」とされた。特に太陽光は技術的に導入しやすく、FIT制度によって急速に普及した。
副作用
急激な拡大はメリット(再エネ比率上昇、投資促進)をもたらしたが、長期的なライフサイクル設計(廃棄・リサイクル・責任分担)までは十分に議論されなかった。
- 廃棄議論が後追いになった理由
当初は 「とにかく普及が先」 という国策優先。
FIT制度が収益性に焦点を当てたため、事業者も「20年間売電すればよい」という短期的視野に偏った。
廃棄時期(20〜30年後)が遠い未来と見なされ、コストや技術開発への関心が薄かった。
- 今どう考えるべきか
必然性として理解する
「エネルギー危機の中で導入を急いだ」という点は歴史的に仕方がなかった部分もある。再エネ普及の初期には、導入推進が優先されがちなのは世界的にも同様。
反省として活かす
廃棄・リサイクルの制度整備が後追いになったことは反省点。今後は「導入から廃棄まで一体で設計する」仕組み(責任の明確化、リサイクル義務、費用積立制度など)が不可欠。
次世代への教訓
太陽光だけでなく、風力タービン、EV用バッテリーなども将来廃棄課題を抱えることとなる。今回の経験を活かして「普及初期から廃棄までのライフサイクルを制度に組み込む」ことが重要だ。
FITによって再エネ導入が加速したことは確かに成果だ。しかし、その陰で廃棄問題が後追いになったのも事実。
この矛盾は「政策の過渡期に生じた宿命」と捉えつつ、今後は 普及・運用・廃棄をワンセットで考える方向へとシフトしていく必要があるだろう。
問題の背景を理解したところで、ここからは再び問題の全体像を把握し直し、現状はどうか、海外での対応事例、課題、今後の見通しまでをみていこう。
1) 問題の全体像(何が問題なのか)
太陽光パネルは「寿命がおよそ25〜30年」とされ、導入ピークから数十年後に大量の廃棄が発生する。パネルは主にガラス、アルミフレーム、シリコンセル、プラスチック(バックシート)、銅や銀などの金属を含み、資源価値がある一方で、適切に処理しないと廃棄物・環境負荷が問題となる。
世界的にはパネル廃棄量が急増する見込みで、2050年までに数千万トン規模(報告によっては約7,800万〜8,800万トン)が予測されている。資源として取り出せれば有用だが、回収・分別・精製のコストと回収インフラが課題となっている。
2) パネルの構成とリサイクル対象(技術的観点)
主な材料: ガラス(重量の大半)、アルミフレーム、シリコンセル(ウェハ)、プラスチック系バックシート、導電性金属(銀、銅)、接着剤や封止材(エポキシ、EVA)など。
リサイクル難易度: ガラスやアルミは比較的リサイクルしやすいが、シリコンセルから高純度の材料を回収する工程や、封止材(EVA)を取り除く工程が技術的・コスト面で難しい。最近は熱分離・化学処理・機械的破砕の組合せが実用化されつつある。これらの工程コストが回収可能な資源価値を上回ることが多いのが実情。
3) 日本の現状(制度・実務)
制度的検討の進展: 近年、日本政府(環境省・経産省)は太陽光発電設備の廃棄・リサイクルを巡る検討を進めている。2024年の循環型社会形成計画で「義務的リサイクル制度の活用」を検討する旨が示され、環境省や資源エネルギー庁でワーキンググループ/小委員会が設置され、制度案が議論されている(既設・新設を含む生産者責任の扱いなどが論点)。
現行の実務的課題: 多くの既設パネルは導入から年数が経っておらず、廃棄はまだ本格化していない一方で、事業者の交換・除却やFIT事業終了に伴う処理の責任所在、輸入パネル(海外メーカー)の扱い、費用負担の在り方などが整理されていない。これが制度設計を難しくしている要因。
4) 諸外国の対応例(代表的なもの)
欧州連合(EU) — WEEE 指令の枠組み
EUは家電系廃棄物(WEEE:Waste Electrical and Electronic Equipment)指令で電気電子機器の廃棄処理・回収を規定している。太陽光パネルはWEEEの枠組みや個別規則で扱われ、メーカーや輸入業者に回収責任(拡大生産者責任:EPR)を課す国が多い。EUは循環経済の観点から回収率目標や処理基準を設定しています。
アメリカ(州ごと)
連邦で統一された太陽光パネルのリサイクル義務は未だ限定的だが、州レベルの立法が活発化している。カリフォルニア州などではパネル廃棄の管理やリサイクル費用を扱う法案が提案・成立の過程にあり、太陽光パネルのリサイクル費用を事前徴収する仕組み(設置時に負担を積み立て)が検討されている。産業主導の回収網や民間リサイクル事業も立ち上がっている。
中国
世界最大の生産国である中国は、国内での廃棄対策とリサイクルインフラ整備を進める計画を打ち出しており、業界でのリサイクル事業の立ち上げが報告されているが、まだ市場規模は発展途上だ。大規模な導入国であるため、政策の動向が国際的な供給チェーンに影響を及ぼす。
産業・民間の取組
リサイクル専業企業や製造側のリサイクル投資(例:再循環ガラス工場や分解ラインの増設)が進んでおり、これを補助する形で政府支援や補助金、企業間連携が進みつつある(米国の事例等)。
5) 主な課題(日本・世界共通)
・経済性の欠如: 回収・分解・精製工程のコストが高く、資源価格では回収投資を回収しにくい。
・回収の難しさ: パネルは分散設置(住宅屋根、遠隔地のメガソーラー)で回収費・運搬コストが高い。
・責任の所在が不明瞭: メーカー・設置者・土地所有者・FIT期間終了後の事業者の負担が不明確。
・規格・表示の不足: 含有材料や分解手順の情報がパネルメーカーごとにバラバラで追跡が難しい。
・有害物質管理: 一部のパネル・部材における有害物質(希少金属の加工残渣や一部化学物質)管理が必要。
6) 今後の見通し(短中長期)
短期(今〜3年): 制度設計の議論(拡大生産者責任:EPRの採用・費用負担の方法・回収スキーム)が各国・各州で加速する。日本でもワーキンググループの議論が続き、既設パネルの扱いを巡る法的調整が注目される。
中期(3〜10年): 廃棄ピークの初期段階に入り、リサイクル需要が実体化。専業リサイクル企業や再資源化設備(ガラス再生、金属回収等)への投資が増加すると予想される。市場規模予測では太陽光パネルのリサイクル市場が年率二桁成長するとの見方もある。
長期(10年以上): 2050年にかけて累積廃棄量は非常に大きくなるため、効率的なEPR制度・設計段階でのリサイクル配慮・国際的な資源循環サプライチェーンが確立されれば、資源循環による原料供給の一助になる。逆に制度や投資が遅れると、埋立や不適正処理による環境負荷リスクが高まる。
7) 具体的な政策・事業の方向性
拡大生産者責任(EPR)の導入: 新設のみならず既設分を含めた負担の在り方(例:設置時徴収、製造量に応じた拠出など)を明確化。複数の国・州でEPRが採用されていることが実務上の参考になる。
製品登録・トレーサビリティ: パネルの含有材料や分解方法を登録し、後年の回収を容易にする。日本のFIT事業認定段階から物性情報を把握する提案もある。
回収インセンティブと物流整備: 地方での回収拠点整備や運搬費の補助、自治体と連携した回収スキーム構築。
技術支援と産業育成: ガラス再利用やシリコン再生などの技術開発・商用化支援。既に民間で大規模な再生ガラス工場等の投資計画も出ている。
リユース(リパーパス)推進: 寿命前に性能低下で交換されたパネルの検査・再利用を促す。
国際協調: 大量の廃棄が想定される中で、原料の国際循環や廃棄物越境問題に備える国際ルール作りも重要。
最後に
太陽光発電はカーボン削減で重要だが、“設置後の廃棄”という課題は必ず訪れるため、なるべく早い段階での回収・リサイクルの制度・産業基盤を整えることが重要となる。
制度設計の議論を積極的に進めてもらい、今後の法整備や産業投資の動向を見守りたい。
発電事業の採算性を保ちながら廃棄・リサイクルの費用も担うのは簡単ではないが、私も事業者の一人として、最後までしっかりと責任を果たすつもりだ。
※フリーマン柴賢二郎の著書をアマゾンで販売中です。
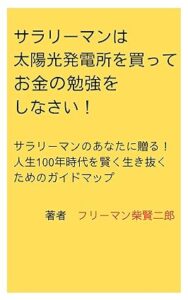
ドライブ・(ウィズ)・マイ・マザー | フリーマン柴賢二郎 | 小説・サブカルチャー | Kindleストア | Amazon