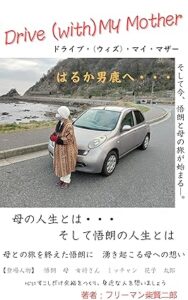フリーマン柴賢二郎の流儀
~そよ風に吹かれて、ゆっくりと歩いていこう~
世の中に起きている不思議なことや、
ふと浮かんだ疑問などをゆる~く書き綴る
何の専門家でもない私が経済的・時間的・人間関係の自由を得て、
人生のこと、世の中のこと、幸せについてなど、
一般庶民の目線で考える
名目金利と実質金利の違いをやさしく解説|お金の「本当の価値」を見抜く視点
名目金利とは「見た目の金利」
ニュースや銀行の広告でよく目にする「金利」という言葉には、実は2種類ある。
それが「名目金利」と「実質金利」である。
まず名目金利とは、銀行などが表示している“そのままの金利”のことだ。
たとえば、100万円を銀行に預けて1年後に1%の利息がつくとすれば、1万円が増える。
これが名目金利1%である。
名目という言葉には「名前だけの」「表面的な」という意味がある。
つまり名目金利とは、お金が“額面上どれだけ増えるか”を示しているにすぎない。
実質金利とは「物価を考慮した本当の金利」
しかし、金利を考えるうえで重要なのは「物価の変化」である。
たとえば、1年前に100円で買えたジュースが今は110円になっていたとしよう。
お金が1%増えたとしても、物価が10%上がっていれば実際には損をしている。
このように、名目の増え方から物価上昇(=インフレ率)を差し引いたものが「実質金利」である。
式にするとこうなる。
実質金利 ≒ 名目金利 − 物価上昇率
名目金利が2%で物価が1%上がれば実質金利は1%。
逆に、名目金利が1%でも物価が2%上がれば、実質金利はマイナス1%。つまり、お金は増えているように見えて実は価値が下がっているのだ。
インフレとデフレで変わるお金の価値
インフレ(物価上昇)のとき、実質金利は下がりやすい。
物価が5%上がっているのに銀行の預金金利が1%しかなければ、実質金利はマイナス4%。
預けていてもお金の“購買力”が減ってしまう。
一方、デフレ(物価下落)のときは、同じ名目金利でも実質金利が高くなる。
物価が2%下がっていて名目金利が1%なら、実質金利は+3%。
モノの値段が下がっている分、お金の価値が実質的に上がるということだ。
このため、インフレ期は借金をしている人に有利で、預金者には不利になる。
借りたお金の実質的な価値が下がるからである。
日本とアメリカの金利を比べてみる
日本では長くデフレや低インフレが続いてきたため、名目金利がほとんど上がらず、実質金利がプラスで推移することも多かった。
一方、アメリカのようにインフレが進む国では、中央銀行が金利を大きく上げて実質金利を調整する。
つまり、金利政策とは単なる数字の操作ではなく、実質金利を通して経済全体のバランスを取る重要な仕組みなのである。
投資や貯金で見るべきは「実質金利」
投資や資産運用を考える人にとって、この実質金利は欠かせない指標だ。
名目金利だけを見て「利回りが高い」と判断しても、物価上昇に追いつかなければ実質的に損をしていることもある。
たとえば、年利1%の国債を買っても、物価が2%上がるなら実質的には年1%のマイナスである。
逆に、物価が上がらなければ同じ1%でも実質的にプラスになる。
だからこそ、「金利」だけでなく「物価」も一緒に見ることが重要なのだ。
まとめ|数字よりも「価値」で判断しよう
名目金利は「見た目の数字」、実質金利は「お金の本当の価値」を示す。
同じ1%でも、物価の動き次第で意味はまったく変わる。
ニュースで「金利が上がった」「物価が上がった」と聞いたとき、その裏にある実質的な影響を考える習慣を持てば、経済ニュースがぐっと身近に感じられるだろう。
お金の世界では、数字よりも「価値」を見抜くことこそが、本当の知恵なのである。
※フリーマン柴賢二郎の著書をアマゾンで販売中です。
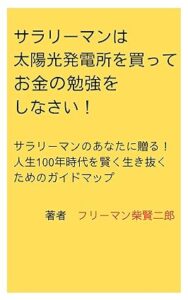
ドライブ・(ウィズ)・マイ・マザー | フリーマン柴賢二郎 | 小説・サブカルチャー | Kindleストア | Amazon