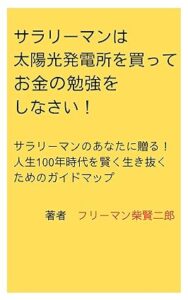フリーマン柴賢二郎の流儀
~そよ風に吹かれて、ゆっくりと歩いていこう~
世の中に起きている不思議なことや、独り言などをゆる~く書き綴る
何の専門家でもない私が経済的自由を得て、人生のこと、世の中のこと、
幸せについてなど、一般庶民の目線で考える
再生可能エネルギーの蓄電所 活発化
再生可能エネルギーに代表される太陽光発電は、昼間すなわち太陽が出ていれば発電して電気を供給できるが、太陽が隠れる夜間では発電してくれないため、電気を供給することができない。
しかし、昼間に発電した電気を蓄電池に貯めておくことができれば、夜間に供給することができる。
誰でも知っていることだが、家庭用の蓄電池は補助金もあり普及が進んでいる。
ところが産業用の蓄電池となると、太陽光発電設備の普及に全く追いついていない。
そのため地域によっては出力制御をかけて発電させないようにしないといけないところもあり、電気を捨てていると言ってよい。
この問題を解決するべく蓄電設備の普及がはじまった。
大規模な蓄電設備を作る技術が間に合わなかったのが原因かよくわからないが、太陽光パネルの設置は急速に進んだ反面、蓄電設備の普及はかなり遅かったように思う。
それがここへきて、ようやく蓄電設備の普及が急速に進みだしたのだ。
政府は2025年2月に閣議決定した第7次エネルギー基本計画で、電源構成に占める再生可能エネルギーを2040年度までに40~50%にする目標を掲げた。
この目標の達成には蓄電設備の設置の普及は欠かせない。
蓄電設備の設置は、太陽光パネルの設置ほど場所を選ばないといった利点がある。
日陰でも全く問題ないのだ。
さらに、必要とするスペースとしては、今の技術でも太陽光パネル設置面積の20分の1で済むそうだ。
蓄電設備が注目され追い風が吹いてくると、そこに商機を見出した企業が続々と参入してくる。
ENEOSホールディングスや関西電力などといったエネルギー関連企業が先行していたが、異業種からの参入も広がっている。
KDDIは2027年までに約60億円を投資して10か所以上の蓄電設備を稼働させる予定。
その第1号として、2025年の秋頃に栃木県内で稼働させる。
ほかの場所にも蓄電設備用に土地を押さえ始めている。
電気が安い昼間に蓄電しておき、電気が高くなる夕方以降に放電して価格差で利益を得るほか、自社の太陽光発電所の電気を昼間に貯めて、夜間に基地局やデータセンターで使う考えもある。
三井住友ファイナンス&リースは、2030年度までに大型蓄電所に2000億円を投資する。
大規模な蓄電設備の設置を20~30か所で進め、2027年度以降から稼働を始める。
自社の太陽光発電所の出力制御がかかる時の電気を蓄電所に貯めるほか、他社が蓄電設備を開発するための資金の貸し付けも始めた。
三菱HCキャピタルは2030年までに1000億円を投資して蓄電設備の設置を進める。
また、それらの用地開発に向けて不動産業界も動き出している。
送配電網を整備する会社も活気づいてくるはずだ。
現時点では再生可能エネルギーの出力変動を補うだけの蓄電設備の稼働は足りていない。
そのため企業は初期投資した分を回収しやすい反面、市場に売る電気は高い値段が付きやすくなってしまう。
しかし参入者が増えるに従い競争が激しくなれば、市場に出回る電気も増え、値段も安くなる期待が持てる。
今後、AI産業の拡大に伴い、必要となる電気は確実に増えていくことになる。
地球温暖化の抑制と合わせ、再生可能エネルギーの普及を望む。
ところで我が家の屋根にも太陽光パネルが設置されているが、蓄電池はまだ設置していない。
昨年FITが終了してしまい、余剰となった電気の買い取り価格が大幅に安くなってしまった。
大規模停電への備えも考えあわせ、いつ蓄電池を買おうか思案中である。
※ 「サラリーマンは太陽光発電所を買ってお金の勉強をしなさい!」という著書をアマゾンで販売中です。太陽光発電投資を検討中または運営中の方に役立つ情報を掲載しております。