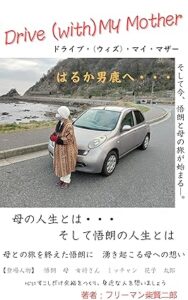フリーマン柴賢二郎の流儀
~そよ風に吹かれて、ゆっくりと歩いていこう~
世の中に起きている不思議なことや、独り言などをゆる~く書き綴る
何の専門家でもない私が経済的自由を得て、人生のこと、世の中のこと、
幸せについてなど、一般庶民の目線で考える
中国、ロシア、北朝鮮の3首脳が一同に会する不気味な光景
2025年9月3日、中国・北京で行われた軍事パレードにて、中国の習近平主席、ロシアのプーチン大統領、北朝鮮のキム・ジョンウン総書記の3首脳が一同に会する光景がテレビで放映された。
世界で最も不気味なこの3人が並んで笑顔で手を振っている光景が、世界に何を突き付けているのか、私なりにまとめてみたい。
軍事パレードの概要
目的: 抗日戦争勝利80年記念、国家統一と歴史的正統性の強調
第二次世界大戦終結と日本の降伏から80年を記念する意味合いを持ち、中国の歴史的正統性と国家統一を強調する場
場所: 北京・天安門広場、長安街(午前9時開始)
規模: 約12,000人の人民解放軍兵士が参加し、行進と装備展示が行われた
参加者: 習近平主席、プーチン、金正恩ほか各国首脳(西側諸国からの参加はほとんどない)
兵器展示:極超音速ミサイル、ICBM、ドローン、ステルス無人機など
演説内容:平和か戦争かの選択、対話重視、覇権主義への反対
3首脳が一同に会した狙いは何か
簡潔にまとめると、「西側諸国に対する牽制」、「国内的な権威強化」、「戦略的利益の共有」を同時に達成するための「政治ショー」であり、国際秩序の分断を鮮明にする象徴的な出来事であった。
具体的には、
- 対外的メッセージ:西側への牽制
アメリカや日本、欧州など「西側主導の国際秩序」に対抗する姿勢を強調。
軍事力を誇示する場に3首脳が並ぶことで、「中露朝が事実上の戦略的パートナーシップを強めている」ことを示す。
特に台湾問題・ウクライナ戦争・朝鮮半島情勢といった「火種」に関して、協調する意思を暗に発信している。
- 国内向け効果:権威と体制の正当化
習近平にとっては「抗日戦争勝利80年」の節目を利用し、自らを歴史の正統な継承者として演出する。
プーチンはウクライナ戦争で孤立を深める中で「強力な友がいる」ことを国内に示せる。
金正恩も経済制裁や外交的孤立を打破し、「大国と並び立つ指導者」として国内向けに威信を高められる。
- 戦略的利害の一致
エネルギーと経済:ロシアから中国・北朝鮮へエネルギー供給、対米制裁回避の協力。
軍事技術:兵器や軍事ノウハウの相互提供の可能性。
外交カード:3国がまとまることで、国際社会との交渉で発言力を増す。
- 「反米権威主義ブロック」の演出
NATOや日米同盟に対抗する「もう一つの陣営」を演出。
実際には利害が完全に一致しているわけではないが、共通して「現状の国際秩序を自分たちに有利に変えたい」という意図を共有している。
欧米の反応はどうか?
一言でいえば 「強い警戒と批判」。
簡潔にまとめると、欧米にとって「権威主義的な対抗軸」が視覚的に示された瞬間であり、インド太平洋戦略やNATOの結束をさらに正当化するきっかけとなった。
具体的には、
- アメリカ
強い警戒感
軍事的には、インド太平洋地域での同盟強化(日米韓・AUKUSなど)を一層推進する口実になった。
- ヨーロッパ(EU・NATO)
NATO関係者は「権威主義陣営の軍事的結束」と受け止め、対ロ制裁・対中警戒を再確認した。
特にウクライナ戦争のさなか、ロシアのプーチンが堂々と北京で歓迎される姿に「国際孤立どころか、新たな後ろ盾を得ている」と懸念が広がった。
EU外交筋からは「中国が平和を語りながら、実際はロシア・北朝鮮と連帯する矛盾」と批判している。
そもそもこの3国は信頼関係にあるのか?
この3国の関係は、「信頼関係」にあるわけではなくむしろ「必要に迫られた戦略的な共闘」であり、「孤立と不安から生まれた便宜的な結束」と表現するのが正確だ。
つまり「敵が同じだから手を組んでいる」に過ぎず、利害が食い違えば簡単に不協和音が表面化する脆い関係である。
具体的には、
歴史的背景と相互不信
【中国とロシアの関係】
1950年代は同盟関係だったが、1960年代に「中ソ対立」となり、国境紛争まで発生。
今日でも「対等なパートナー」というより、経済力で優位な中国にロシアが依存している側面が強い。
【中国と北朝鮮】
朝鮮戦争で中国が軍を送った歴史的関係はあるが、その後は不信が根強い。
北朝鮮は「中国に従属しすぎる」ことを嫌い、自主独立を誇示してきた。
中国も、北朝鮮の挑発的行動に振り回されることを警戒している。
【ロシアと北朝鮮】
ソ連時代は庇護関係にあったが、冷戦終結後は関係が冷え込み、経済支援も途絶えた。
最近は制裁回避や武器取引で再接近しているが、相互に利用している色が濃い。
現在の3国関係の特徴
【共通点】
米国・西側に対抗したい。
国際社会で孤立しているため、互いに「孤立を和らげる存在」として利用できる。
体制維持(共産党一党支配、権威主義的支配)という共通利益がある。
【相違点】
中国:世界経済への依存度が高く、過度に「悪の枢軸」と見られるのは避けたい。
ロシア:ウクライナ戦争で追い詰められ、中国に経済的に依存する構図に不満もある。
北朝鮮:自らが「小国」として軽視されることを嫌い、両国を信用しきれていない。
日本は何を警戒するべきか?
最も警戒すべきは、「3国の軍事的連携」および「外交・経済での圧力」が同時に強まること。特に、台湾・朝鮮半島・北方領土の、正対する3か所で危機が連動するシナリオ。
日本は「一国では対応できないリスク」が増えるため、同盟・多国間協力を基盤にした抑止力強化 が不可欠となる。
日本が取り得る対応として、具体的には、
日米同盟の深化:インド太平洋における抑止力を強化。
日米韓の協力:北朝鮮ミサイル防衛や情報共有を強化。
防衛力整備:反撃能力やサイバー防衛力の向上。
経済安全保障:エネルギー・半導体・食料など供給網の多角化。
外交的取り組み:ASEANやインド、欧州との連携を広げ、孤立を避ける。
まとめ
中国は経済力を背景に覇権拡大を狙い、ロシアはウクライナ戦争で孤立を深め、北朝鮮は体制維持のために存在感を誇示する。
信頼に基づく同盟ではなく、孤立と不安に背中を押された「便宜的な結束」にすぎないのは明らかだ。
とはいえ、日本にとって看過できないのは、この不安定な協力関係が尖閣諸島、台湾、朝鮮半島、北方領土といった現実の脅威を生む点である。
加えて、エネルギーやレアアースの供給制限、サイバー攻撃、歴史問題を利用した世論戦など、軍事以外の分野でも圧力が高まる可能性がある。
日本は同盟国とともに抑止力を整えると同時に、経済安全保障や外交的な発信力を高めていかなければならない。
※フリーマン柴賢二郎の著書をアマゾンで販売中です。
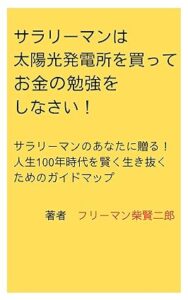
ドライブ・(ウィズ)・マイ・マザー | フリーマン柴賢二郎 | 小説・サブカルチャー | Kindleストア | Amazon