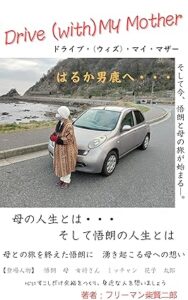フリーマン柴賢二郎の流儀
~そよ風に吹かれて、ゆっくりと歩いていこう~
世の中に起きている不思議なことや、独り言などをゆる~く書き綴る
何の専門家でもない私が経済的自由を得て、人生のこと、世の中のこと、
幸せについてなど、一般庶民の目線で考える
「TICAD」について学ぶ
先日、横浜で「TICAD9」が開催された。
この報道を受け、いい機会なので今回は「TICAD」について勉強し、私なり投資にどう活かせるか、という視点でまとめてみたい。
そもそも「TICAD」とはどういうものか?
TICAD(ティカード)は、Tokyo International Conference on African Developmentの略語で、日本政府が主導して開催している、アフリカの開発をテーマにした国際会議。
日本とアフリカが「共に成長していく」ための国際的な対話と協力の場。
概要
開始:1993年に第1回が東京で開催された
主催:日本政府(外務省)、国連、国連開発計画(UNDP)、世界銀行、アフリカ連合委員会(AUC)などの国際機関
目的:
・アフリカ諸国の開発課題の解決を国際社会と協力して進める
・アフリカの「自助努力」を尊重しつつ、国際社会が「パートナーシップ」として支援す る
・経済成長・投資促進、人材育成、平和と安定などを包括的に議論
特徴:
・日本発の国際会議としてアフリカ諸国からの信頼が厚い
・欧米や中国とは違い、「人間中心の開発支援(人材育成・制度整備・インフラ整備)」を重視している
・政治・経済だけでなく、教育、医療、気候変動、農業など幅広い分野が対象
・おおむね3年ごとに開催され、日本だけでなくアフリカ各国でも行われている
「TICAD」を通した日本の狙いとは何か?
ひとことで言うなれば、「アフリカを支援しながら、日本の外交的影響力・経済的利益・国際的地位を高める」ことにある。
具体的には、
- 外交・国際政治上の狙い
国際的プレゼンスの向上
→ 日本がアフリカの開発支援に積極的に関わることで、国際社会での信頼と発言力を強める。
国連安保理改革への支持確保
→ アフリカ諸国は国連加盟国の約3分の1を占めるため、安保理常任理事国入りを目指す日本にとって重要な票田となっている。
中国や欧米とのバランス
→ 中国は「一帯一路」でアフリカへの投資を拡大、欧米も影響力を保持。日本も独自の「人間中心の支援」で存在感を示したい。
- 経済上の狙い
市場開拓
→ 人口増加・経済成長が著しいアフリカは、将来の巨大市場。日本企業にとって輸出・投資の拡大先。
資源確保
→ アフリカはレアメタルやエネルギー資源が豊富。日本のエネルギー安全保障や産業競争力に直結する。
インフラ輸出
→ 日本は鉄道、道路、港湾、エネルギーなどのインフラ技術をアフリカに売り込みたい。
- ソフトパワー・人材戦略
人材育成で信頼関係を築く
→ 留学生受け入れ、技術研修、医療支援などを通じて「日本に恩義を持つ人材」を増やし、長期的な関係性を確保。
「質の高い成長」イメージの浸透
→ 単なる資金援助ではなく「持続可能性」「人間中心」を掲げ、日本らしい支援モデルを示す。
日本の動きに対して欧米や中国の反応はどうか?
欧米は「協力しつつ牽制」、中国は「競争しつつ批判」、という反応が中心となっている。
具体的には、
- 欧米の反応
【ポジティブな側面】
協調の場として評価
→ 欧米諸国(特にフランス・EU)は、アフリカでの日本の取り組みを歓迎する傾向がある。日本が資金・技術で支援することは、欧米の負担を軽減するから。
共同事業も存在
→ 医療・保健・教育などの分野では、EUや世界銀行と日本が連携するケースも多い。
【牽制的な側面】
「影響力の奪い合い」
→ 欧米(特に旧宗主国フランス)はアフリカでの影響力を維持したい。日本が存在感を強めると、自国の影響力低下につながるという懸念もある。
市場競争
→ インフラや企業投資で日本企業が参入することは、欧米企業にとって競争相手になる。
- 中国の反応
【警戒】
直接のライバル視
→中国は「一帯一路」を通じて巨額のインフラ投資をしており、アフリカを戦略的に重視。日本のTICADは、自国の影響力に対する「対抗軸」として見ている。
外交的競合
→ アフリカの票を国連などで取り込むことは中国にとっても重要。日本が安保理常任理事国入りを目指す姿勢には強い警戒感がある。
皮肉や批判
→ 中国メディアは「日本は約束した援助を十分に実行していない」「中国ほどの資金力はない」などと指摘している。
「人間中心の開発」という日本の理念を「実際には経済的利権目的だ」と批判する論調もある。
- アフリカ諸国から見た違い
欧米:旧宗主国としての歴史的な影響力が強いが、植民地支配の記憶が重荷になる面もある。
中国:資金力・スピード感は圧倒的だが、債務問題や現地雇用を奪うという不満も増えている。
日本(TICAD):資金量は小さいが、技術・人材育成・持続性に重きを置き、「信頼できる長期的パートナー」という評価が比較的多い。
「TICAD」を通じたアフリカ各国から日本への反応はどうか?
全体的に「好意的・信頼寄り」で、「信頼できる、誠実なパートナー」、「もっと大きく・早く関与してほしい」、という二面性を持った評価をしている。
具体的には、
- 好意的な反応
「対等なパートナー」という評価
→ 欧米や中国に比べて、日本は「押しつけがましくない」「政治的干渉が少ない」と見られ、信頼感が強い。
人材育成・教育支援の評価
→ 日本の奨学金で留学したり、JICAの研修を受けた人材が現地でリーダーになっており、日本への好意的なつながりを生んでいる。
「質の高いインフラ」への信頼
→ 中国製インフラは「安いが壊れやすい」と言われることもあり、日本の技術は「耐久性がある」「安全」と評価されている。
長期的視点の支援
→ 債務を背負わせず、農業・医療・教育といった基礎的な分野に投資してくれる点は高評価。
- 期待と要望
支援規模の拡大
→ 中国の巨額投資に比べると日本の資金規模は小さく、「もっと投資を増やしてほしい」という声もある。
スピード感への要望
→ 日本のプロジェクトは丁寧だが時間がかかるため、「即効性がほしい」という不満も出る。
民間企業の進出不足
→ 政府やJICAの支援はあるが、日本企業の投資が少なく、「ビジネスパートナーとしての存在感」をもっと求める声がある。
- 批判や懸念
「日本は約束を守るが控えめ」
→ アフリカの一部からは「日本は真面目だが、もっと積極的に動いてほしい」との指摘もある。
中国との比較で見劣り
→ インフラ建設のスピード・規模ではどうしても中国に見劣りするため、「実利的な部分では中国に頼るしかない」という現実もある。
現地雇用の広がりに課題
→ 日本の企業進出が少ないため、雇用創出効果は中国や欧米に比べて限定的。
日本人として「TICAD」に何を期待できるのか?
ひとことで言うなれば、「世界に貢献しながら、日本自身の未来も豊かにする場としての役割をTICADに期待できる」と言える。
具体的には、
- 国際的な評価と存在感の向上
日本は経済規模に比べて「外交的な存在感が薄い」と言われがちである。
TICADを通じて「誠実で信頼できる国」というイメージを国際社会に示すことは、日本人にとって誇りや安心感につながる。
特に国連安保理改革などで、日本の立場を支える「票田づくり」にも期待できる。
- 日本経済へのメリット
アフリカは人口増加・経済成長が続く「未来の巨大市場」。
TICADをきっかけに、日本企業がインフラ、エネルギー、IT、農業分野で進出すれば、雇用や経済成長にプラスとなる。
レアメタルや資源の安定確保にもつながり、日本の産業競争力を支える。
- 安全保障・安定への貢献
アフリカの紛争や貧困は、テロ・感染症・難民問題として世界に波及する。
日本が開発や平和構築に関与することは、国際的な不安定要因を減らし、自国の安全にもつながる。
- 人材・文化交流の広がり
アフリカからの留学生や技術研修生が増えることで、日本社会は国際化・多様化が進む。
日本の若者にとっても「アフリカで学び・働く」機会が増え、新しい視野を開ける。
- 日本の価値観を世界に広める
「人間中心の開発」「質の高い成長」という日本らしい支援スタイルを示すことで、国際社会での日本の独自性を確立できる。
日本人として「自分たちの国が世界の役に立っている」という実感は、大きな意義がある。
個人投資家として「TICAD」に何が期待できるのか?
以上をふまえ、最後はやはりこのテーマで締めたい。
- 新興市場(アフリカ)への投資機会
アフリカは人口増加(2050年に世界の4人に1人がアフリカ人)・資源・都市化で「次の成長市場」として注目されている。
TICADを通じて、日本政府や企業が関与を強めると、投資リスクが下がり、市場アクセスの可能性が高まる。
ETFやファンド、アフリカ関連株(資源・農業・インフラなど)への投資の参考になる。
- 日本企業の成長チャンス
インフラ(鉄道、電力、港湾)、再エネ、デジタル(通信・フィンテック)、農業支援などはアフリカで需要拡大。
日本企業がTICADを機に参入し業績が拡大すると日本株への投資妙味が生まれる。
(例:総合商社、建設・プラント企業、金融、通信、医薬品など。)
- 資源・エネルギー関連への注目
アフリカはレアメタル(リチウム・コバルト・ニッケルなど)の宝庫。
EVや再エネ需要の高まりで、これらの資源関連企業の成長期待が高まる。
TICADを通じて日本の資源外交が強まれば、安定調達ができることから関連株の安心材料につながる。
- ESG投資の視点
TICADは「持続可能な開発」「人間中心の成長」を重視している。
ESG(環境・社会・ガバナンス)投資が広がる中、TICADをきっかけに日本企業がSDGs型ビジネスを進めることにより、投資対象としての注目度が上がる。
- リスク分散・国際感覚の獲得
日本株・米国株だけでなく「アフリカ」という新しい投資先を学ぶきっかけとなる。
直接投資しなくても、世界情勢や新興国のダイナミズムを理解することは投資判断の幅を広げることになる。
まとめ
株式ポートフォリオの中で、アフリカの投資信託があれば、小さく組み込んでおく価値がありそうだと見た。
また、総合商社、建設・プラント企業、金融、通信、医薬品などの関連銘柄に対するアンテナを高く持っておきたいと感じた。
※フリーマン柴賢二郎の著書をアマゾンで販売中です。
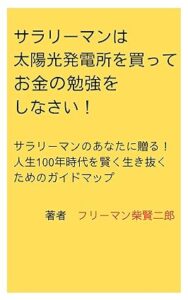
ドライブ・(ウィズ)・マイ・マザー | フリーマン柴賢二郎 | 小説・サブカルチャー | Kindleストア | Amazon