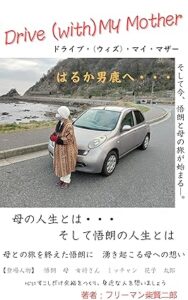フリーマン柴賢二郎の流儀
~そよ風に吹かれて、ゆっくりと歩いていこう~
世の中に起きている不思議なことや、
ふと浮かんだ疑問などをゆる~く書き綴る
何の専門家でもない私が経済的・時間的・人間関係の自由を得て、
人生のこと、世の中のこと、幸せについてなど、
一般庶民の目線で考える
「春闘」と「最低賃金」について
「春闘」と「最低賃金」はどちらも「賃金」に関わる言葉だが、性質・目的・仕組みは大きく異なる。
今回はまず両者を定義し、それぞれの制度的特徴や当事者、実行メカニズムを整理したうえで、比較・相互関係、現代の課題まで掘り下げていきたい。
労働者の生活保障と賃金の底上げをめぐる二つのアプローチを併せて理解することで、賃金政策の全体像を捉えていきたいと思う。
定義と目的(要点)
〇春闘(しゅんとう)・・・
意味: 主に労働組合が春季に行う年間賃上げ交渉の総称で、企業別交渉を横断的に調整・連携することで波及的に賃上げを促す慣行。
目的: 組合員の労働条件改善(定期賃金の引上げ=ベースアップや一時金)と賃金水準の維持・向上。年次の慣行として賃上げ要求・交渉を集中させ、景気や物価の動向に応じた賃金改定を図る。
〇最低賃金(さいていちんぎん)・・・
意味: 法律で定められた賃金の下限(法定最賃)。使用者はその額未満の賃金を支払うことが禁じられる。
目的: 労働者の最低限の生活を保障し、極端な低賃金競争を抑制する社会的セーフティネット。勤労者全体の底辺を支える機能を持つ。
制度と実行の仕組み
〇春闘の仕組み・・・
主体: 企業別の労働組合(多くは企業単位の組合)、それらが加盟する労働組合連合体や産業別協調体。
方法: 各企業での団体交渉を軸に、産業横断的・地域横断的な賃上げ目標を掲げる。争議(ストや宣伝、統一行動)を背景に「パターン(目安)賃上げ」を形成し、中小企業にも波及することを狙う。要求項目はベースアップ(恒常的賃上げ)と一時金(賞与的支払い)等が典型。
法的位置づけ: 労使の自主的な団体交渉(労働組合法に基づく)であり、法律で一律の賃金額を決めるものではない。成果は合意による。
〇最低賃金の仕組み・・・
主体: 政府(関連省庁)とその下に設置された審議会や委員会(労働者側代表、使用者側代表、公益代表などで構成)による審議を経て決定される。
形態: 多くの国で地域別・産業別の制度があり、日本の場合は都道府県ごとの地域別最低賃金に加え、必要に応じて産業別の特定最低賃金が設定される。
法的効力: 法令に基づく強い拘束力があり、使用者が最低賃金を下回る賃金を支払えば罰則や追徴が発生する(法的救済手段がある)。改定は定期的(例:年に1回程度の見直し)に行われるのが通例。
比較(ポイント別)
〇法的拘束力・・・
春闘: 合意に基づく自主的制度。法で賃金水準を強制するわけではない。
最低賃金: 法律による強制力を持つ下限。
〇対象範囲・・・
春闘: 主に組合員が直接対象。ただし大手企業での賃上げが賃金相場を引き上げることで非組合員にも波及することがある。
最低賃金: 法の適用を受ける全ての労働者(パート、アルバイト含む)が対象。
〇決定主体とプロセス・・・
春闘: 労使交渉(労働組合 ⇄ 企業経営)。産業別の連携で交渉力を高める。
最低賃金: 政府の審議会など公的プロセス(労使代表+公益代表)による行政決定。
〇目的の違い・・・
春闘: 賃金水準の引き上げと組合員の利益確保(分配改善)。
最低賃金: 最低限度の生活保障と賃下げ抑制(社会的底上げ)。
〇成果の形(短期/長期)・・・
春闘: ベースアップは長期的な恒常的引上げ、一時金は一時的な給付。交渉の結果による変動が大きい。
最低賃金: 法定額の改定という形で明確に全体に適用される。
〇経済への影響・・・
春闘: 組合の力次第で実現する賃上げが消費拡大や労働者のモラル向上を招くことが期待される。一方、企業負担増が課題となる。
最低賃金: 低所得者の所得を直接押し上げるため貧困削減に有効だが、急激な引上げは企業のコスト上昇や雇用調整圧力を招く可能性が議論される。
相互作用と現代的課題
〇相互作用・・・
春闘と最低賃金は競合するものではなく、むしろ補完的な関係にある。
最低賃金は賃金の下限を法的に保証し、春闘はその上の賃金水準(特に正社員や組合員のベース)を引き上げる役割を担う。
春闘の結果として形成される賃上げの「目安」が下方層まで波及すれば、最低賃金に頼らない自律的な賃上げが進む。
逆に最低賃金が上がれば、春闘側の交渉目標や企業側の負担感に影響を与える。
〇現代的課題・・・
組合員割合の低下と非正規雇用の増加: 春闘は企業別の組合が中心のため、非正規労働者・非組合員の低賃金層への直接的効果は限定的。
地域間・産業間の格差: 最低賃金は地域差があり、生活費や雇用構造の違いをどう反映させるかが課題。
物価・インフレとの関係: インフレ期には賃上げ圧力が高まるが、企業収益とのバランスをどう取るか。
デジタル化・自動化: 労働需要の構造変化は、低賃金労働者の雇用機会に影響を与え、最低賃金や春闘戦略の在り方を再考させる。
まとめ — 併用で機能する賃金政策
春闘は労使の自主的交渉を通じて賃金体系を上方に引き上げる社会的慣行であり、一方の最低賃金は法律によって賃金の底を支える制度である。
どちらか一方だけでは賃金の公平性や生活保障に限界があるため、両者は補完的に機能することが望ましい。
具体的には、政府は最低賃金を地域実情と生活コストに応じて適正に見直し、労働組合は非正規労働者や中小企業にも波及するベースアップを追求する——こうした相互補完的な取り組みが、格差縮小と持続的な賃金成長につながると考えられる。
※フリーマン柴賢二郎の著書をアマゾンで販売中です。
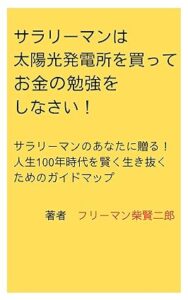
ドライブ・(ウィズ)・マイ・マザー | フリーマン柴賢二郎 | 小説・サブカルチャー | Kindleストア | Amazon