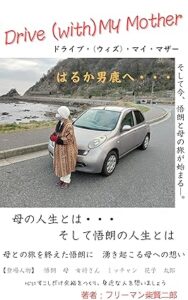フリーマン柴賢二郎の流儀
~そよ風に吹かれて、ゆっくりと歩いていこう~
世の中に起きている不思議なことや、
ふと浮かんだ疑問などをゆる~く書き綴る
何の専門家でもない私が経済的・時間的・人間関係の自由を得て、
人生のこと、世の中のこと、幸せについてなど、
一般庶民の目線で考える
「レアアース」について学ぼう
- レアアースとは
定義
鉱物から抽出される金属のうち、周期表でランタン(La)からルテチウム(Lu)までの15元素に、スカンジウム(Sc)とイットリウム(Y)を加えた17元素の総称のこと。
特徴
「希土類」という名前だが、実際には地殻にそこそこ存在する。ただし「分散して存在」するので、採掘・精錬が難しく、結果として「レア」になっている。
- 主な用途
レアアースは「見えないけど必須」な素材である。
電気・電子分野
・ネオジム磁石(Nd): モーター、ハードディスク、EV(電気自動車)
・ユーロピウム(Eu)、テルビウム(Tb): 蛍光体、液晶ディスプレイ
エネルギー分野
・風力発電の強力磁石
・蓄電池、燃料電池の材料
自動車分野
・ハイブリッド車やEVのモーターに必須
防衛・宇宙分野
・ミサイル制御装置、レーダー、光学機器
日常品
・スマートフォン、イヤホン、照明、カメラレンズ
- 世界の産出と供給
産出国ランキング(2020年代)
1,中国(約6割)
2,アメリカ
3,オーストラリア
4,ミャンマー
5,その他(インド、ロシア、ベトナムなど)
中国の優位性
・埋蔵量が豊富
・精錬・分離技術に強みを持つ
・価格調整を通じて世界市場をコントロールできる
- 経済・地政学的側面
・レアアースは「戦略資源」と呼ばれる
・過去に中国が日本向け輸出を制限(2010年尖閣諸島事件後)したことにより世界的にレアアースの重要性が注目された
・米中対立の中で「資源の武器化」が問題視されている
・日本は「代替材料」「リサイクル」「調達先の多様化」に力を入れている
- 技術・環境の課題
採掘の環境負荷
・放射性物質(トリウムなど)が副産物として出る
・採掘による土壌汚染や地下水汚染
精錬の難しさ
・物理的・化学的に分離が難しく、コスト高
リサイクル
・使用済み製品からレアアースを取り出す技術が進歩中
・特に日本はリサイクル技術が世界的に高評価
- 将来展望
需要増大
・EV、再生可能エネルギー、AIデバイスなどの拡大で需要急増
代替技術の研究
・レアアースを使わないモーターの開発
・代替素材の開発
資源戦略
・各国が「サプライチェーンの安全保障」を重視している
・海底鉱床や南極など未利用資源の開発も検討されている
ここまでをまとめてみると、レアアースは・・・
・現代文明の必需品(スマホから戦闘機まで)
・中国が握る戦略資源(国際的交渉のカードになる)
・環境リスクとリサイクル課題(持続可能性とのバランスが重要)
・未来技術のボトルネック(EV、AI、再エネを左右する)
まさに「見えないけど最前線にある資源」と言える。
では、ここからは、日本がレアアースをめぐるこうした状況の中での、課題・期待・戦略
についてまとめる。
- 日本の課題
(1) 中国依存からの脱却
・日本は一時期、レアアース輸入の9割以上を中国に依存していた
・2010年の尖閣諸島事件後、中国が日本向け輸出を制限したことで国内産業に大きな衝撃を受けた
→ 依存度を下げることが最大の課題
(2) コストの高さ
・レアアースの採掘・精錬はコストが高く、商業的に成り立ちにくい
・中国が「低価格輸出」で市場を支配してきたため、日本企業が独自調達するのは経済的に不利
(3) 環境リスク
・レアアースの精錬では放射性物質を含む廃棄物が発生する
・日本国内で大規模に精錬するには、環境対策と社会的合意が必要
- 日本の期待
(1) 技術立国としての強み
・リサイクル技術: 使用済みスマホ、家電からレアアースを回収
・省レアアース技術: モーター設計を工夫して使用量を削減
・代替材料研究: 鉄系やコバルト系などの新素材の開発
(2) 海底資源の可能性
・小笠原諸島や南鳥島周辺の深海レアアース泥は、世界有数の埋蔵量とされる
技術的課題は多いが、将来的には「中国依存を抜け出す切り札」になる可能性が高い
(3) 国際的協力
・オーストラリア、ベトナム、インドなどの資源国と提携
・米国やEUとも「資源サプライチェーン連携」を強化
- 日本の戦略(今後の方向性)
調達先の多様化
・中国一極集中を避け、オーストラリア、インド、アフリカ諸国などからの輸入を拡大する
リサイクル社会の確立
・都市鉱山(使用済みの家電や電子機器から金属資源を回収し再利用する概念のこと)の活用を進め、使用済み家電や車からレアアースを回収する
・使用効率を上げ、資源循環型社会を構築する
技術革新での先手
・「脱レアアース」技術や代替材料研究を推進する
・磁石、モーター、電池といった基盤技術で世界をリードする
深海資源の研究開発
・海洋国家としての強みを活かし、南鳥島のレアアース泥開発を国策レベルで推進する
国際連携と外交戦略
・アメリカ、EU、資源国と協力し、資源の「政治的リスク」を分散する
・資源を「武器化」されにくい仕組みを構築する
日本の課題・期待・戦略をまとめると、
「日本にとってレアアースは 技術立国を支える基盤資源」と言える。
中国依存を脱却するため、調達の多様化・リサイクル・代替技術・海底資源という複数の道を同時に進める必要がある。
将来的には、日本の「技術力+海洋資源+国際連携」が合わさって、資源大国に依存しない強靭な産業基盤を築くことが期待される。
ここまでレアアースについて調べてきたが、もう1段降りて、私のような一般庶民の目線から見たレアアースというものについて述べたい。
正直に言えば、普段の生活の中で「レアアース」という言葉を意識することはほとんどない。
スマートフォンもパソコンも当たり前のように使い、電気自動車や風力発電の話題も耳にするが、その裏に「小さな金属の力」があるなどとは、普段は考えもしない。
しかし、ニュースで「中国が輸出制限をする」とか「日本が海底資源を掘り当てた」と聞くと、どこかで自分の生活ともつながっているのだと気づかされる。
スマホが高くなるかもしれない、車が値上がりするかもしれない、あるいは逆に新しい技術で暮らしがもっと便利になるかもしれない──そんな形で、レアアースは静かに庶民の財布や暮らしに影響を与えているようだ。
また、日本が海底からレアアースを見つけたり、リサイクルで取り出す技術を開発したりしていることを知ると、「資源が乏しい国だからこそ工夫して強くなれるのだ」という誇らしい気持ちにもなる。
目に見えない資源の争奪戦は難しい世界の話のように思えても、最終的にはスマホを使う自分、電気を使う自分に直接つながってくる。
そう考えると、レアアースというのは実は私たちの毎日の暮らしを支える「縁の下の力持ち」なのだということが実感できるのではないか。
※フリーマン柴賢二郎の著書をアマゾンで販売中です。
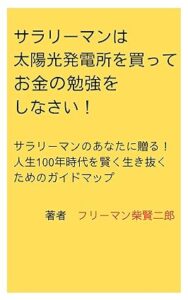
ドライブ・(ウィズ)・マイ・マザー | フリーマン柴賢二郎 | 小説・サブカルチャー | Kindleストア | Amazon